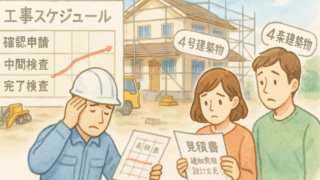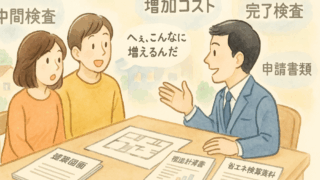耐震特集
耐震特集 耐震補強や間取り変更は要注意!
かつては「確認申請といえば新築のときにだけ必要なもの」と考えられていました。しかし、2025年の法改正で4号特例が廃止・縮小されたことにより、小規模住宅でもリフォームや改修工事の内容によっては確認申請が必要になる時代がやってきました。
「たった数本の筋交いを入れるだけだから申請なんて不要でしょ?」
「壁を取っ払って広いLDKにしたいだけだし…」
そんなふうに思ってリフォーム工事を進めてしまうと、法令違反となってしまう恐れがあります。