白蟻の被害は、一度発生してしまうと建物の寿命や耐震性に大きな影響を及ぼします。しかし、設計段階から対策を講じることで、そのリスクを大きく減らすことが可能です。この章では、白蟻被害を未然に防ぐための建築設計や施工のポイントを、実務的・具体的に解説します。
そもそも白蟻はどこから侵入するのか?
白蟻は基本的に地面から建物へと侵入します。そのルートとして多いのが次のようなパターンです。
| 侵入経路 | 特徴 |
|---|---|
| 基礎の立ち上がりと土台の接合部 | 地面と最も近く、蟻道を作って登ってくる |
| 配管まわりの隙間 | 湿気が多く、わずかな隙間からも侵入可 |
| 玄関・勝手口・ポーチ柱の根元 | 外部との接点が多く、雨水や湿気も集まりやすい |
| 床下点検口・押入れの隅 | 通気が悪く、暗く湿気がこもりやすい |
→ つまり、「湿気」+「地面に接している部分」=要注意エリアということです。
設計段階でできる白蟻対策
ベタ基礎を採用する
ベタ基礎とは、建物の床下全面に鉄筋コンクリートを打設する構造。これにより、白蟻の侵入経路となる地面との接触面を広くかつ密閉性高く遮断できます。
- 布基礎と比較して、侵入しにくい
- 床下の湿気を抑えられ、カビ・腐朽菌の発生も防ぎやすい
- 地震時の耐力も高められる
※ ただし、施工不良(ひび割れ、隙間など)があると逆効果なので要注意です。
基礎パッキン工法で床下通気を確保
「床下がジメジメしている=白蟻にとって理想的な環境」そのため、床下の風通しを良くする設計が非常に重要です。基礎と土台の間に「基礎パッキン(通気部材)」を挟むことで、外気が床下を自然に流れる構造をつくることができます。
- 土台が直接コンクリートと接しないため腐りにくい
- 湿気がこもらない=白蟻が定着しにくい
水まわりの木材は防蟻処理材を使用
浴室・洗面所・キッチンなど、水気の多い場所は特に白蟻被害が集中しやすいエリアです。
設計段階から:
- ヒノキ・ヒバなど防蟻性の高い木材を選ぶ
- 防腐・防蟻処理(加圧注入材など)を施した構造材を使用する
- 水漏れ時の排水経路やメンテナンス性を考慮する
といった「水気」と「白蟻」の両方を意識した部材選定と納まり設計が必要です。
外部からの構造接続部に注意
ウッドデッキ・縁側・ポーチ柱・庇など、外部の木部が基礎や土台と連続している部分は、白蟻が侵入しやすい“橋渡し”になります。
- 外部の木部は構造躯体と切り離す(金物で浮かせる、束石を挟むなど)
- 屋外の木部には防蟻・防腐処理を徹底する
- 雨仕舞を適切に行い、水が溜まらない設計とする
施工時に注意すべきチェックポイント
設計が良くても、施工段階での不備があれば白蟻リスクは高まります。
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 防蟻処理の施工 | 地盤面から1m以内の木材や基礎に、薬剤処理がきちんと施されているか |
| 基礎のひび割れ | コールドジョイント・乾燥収縮などによる微細な隙間が侵入ルートになる |
| 配管まわりのすき間処理 | 給排水管の貫通部がしっかりシールされているか(モルタル・ウレタン等) |
| 床下の清掃状況 | 施工中に残材(木くず、段ボール)が落ちていないか(白蟻の餌になる) |
維持管理も設計段階から想定する
白蟻対策は「建てて終わり」ではなく、点検・予防のしやすさも重要です。
- 床下点検口の位置・広さを確保する
- 換気状況をチェックしやすい基礎の構成をつくる
- 白蟻再処理がしやすいように処理履歴の記録を残す
→ こうした「長く住むための設計配慮」が、将来の白蟻被害を防ぐ“仕掛け”になります。
まとめ:家づくりの「白蟻対策」は設計から始まっている
白蟻は湿気と木材があればどこにでもやってきます。しかし、「入らせない」「住みにくくする」工夫を設計と施工で徹底すれば、白蟻被害のリスクは大きく下げられます。
白蟻を防ぐ家は、丈夫で長持ちし、安心して暮らせる家。
それは、設計者・施工者・住まい手の三者でつくる“チーム戦”なのです。

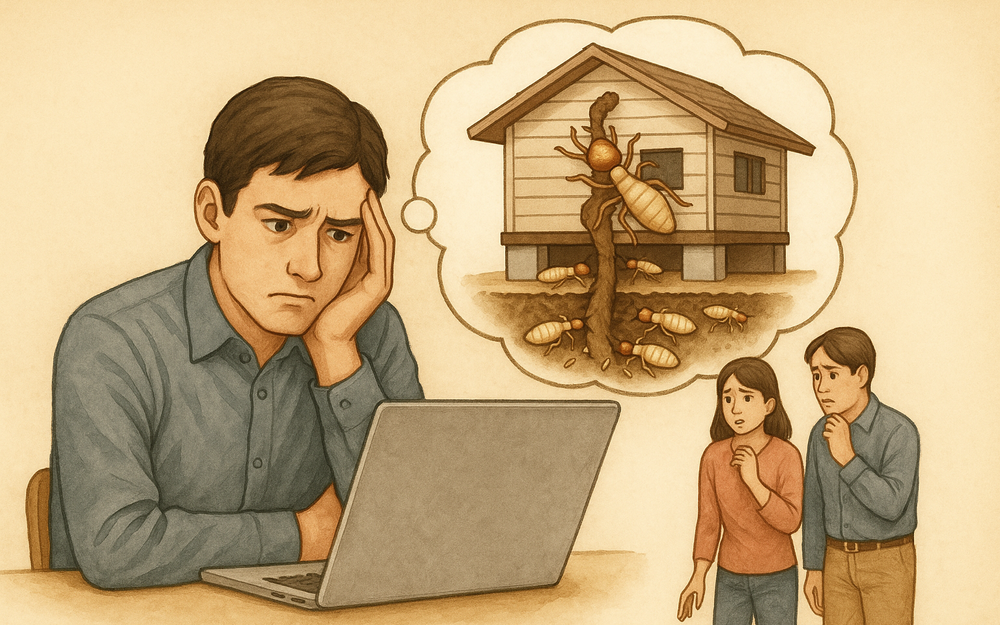
目次