 欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集 調査報告書・意見書の役割
住宅調査で作成される調査報告書と意見書の役割を解説。事実を整理する報告書と、専門家の判断を示す意見書の違いを明確にし、住まい手が冷静に判断するための考え方を建築士の視点で説明します。
 欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集  欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集  欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集 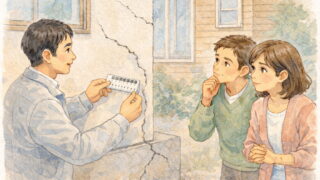 欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集 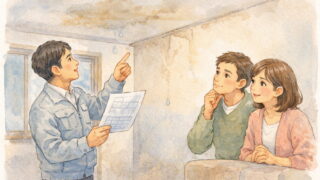 欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集 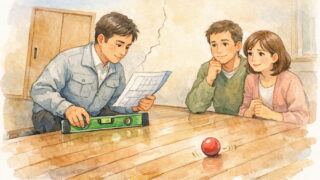 欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集 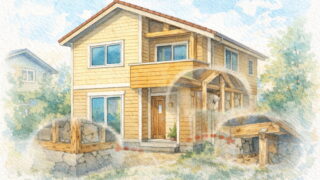 欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集  欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集  欠陥住宅・住宅トラブル特集
欠陥住宅・住宅トラブル特集 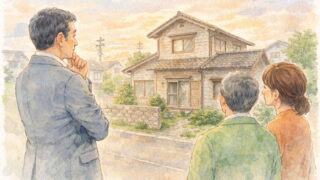 耐震特集
耐震特集